 |
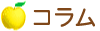 |
【9月号】 |
|
 |
 |
| ● 今月のテーマ 〜音楽的成長と発達〜 |
 |
夏休みは、いかが過されましたか?今年は梅雨空けが遅かったせいか、8月半ばからの猛暑はこたえましたが、皆様は?さて7月に引き続き幼児の音楽環境のお話を、夏休みに読んだ本よりご紹介します。
|
| ○ |
遺伝と環境とは相互に作用しあっている;音楽性というものは、うまれと育ちと両方の所産であって、一方は残りの一方なくしては効力を発揮しないものである。 |
| ○ |
少なくとも、産まれて1年の間が、音楽的になってくる重要な初期の段階であることは確かである。 |
| ○ |
音楽的発達は、子どもたちが、大人と一緒の楽しい音楽的経験に参加する多くの機会を与えられて高められる。 |
| ○ |
子どもは、自分に歌いかけられたり話しかけられたりするなかで、歌ったり話しをすることができるようになっていく。歌うことや話すことの始まりは、子どもがどれだけまわりの人々や自分自身と関係をつくっているかにかかっている。 |
|
教師だけでなく、家庭での親との交わりが、何にもましてやはり大切なんですね。さて、猛暑も過ぎ去り爽やかな風も感じられる様になる9月、気持ちもリフレッシュして、楽しいレッスンをいたしましょう!
[音楽的成長と発達 T・マクドナルド&M・サイモンズ共著 より]
|
 |
 |
 |
 |
| 幼児のための音楽教育で、広まっているリトミックですが、日本人で初めてとりいれたのは、なんと歌舞伎の「市川左団次」でした。彼は、1906年(明治42年)ロンドンの俳優学校でダルクローズのレッスンを受け、自ら創立した研究劇団「自由劇場」の俳優たちの養成に、リトミックをとりいれました。その後、作曲家の山田耕作、劇作家の小山内薫、舞踏家の伊藤達郎、石井獏などがダルクローズのリトミックを学びました。これが本来の目的である、音楽教育法の革命として教育界に導入されたのは、大正の末になります。 |
 |
|
|
 |